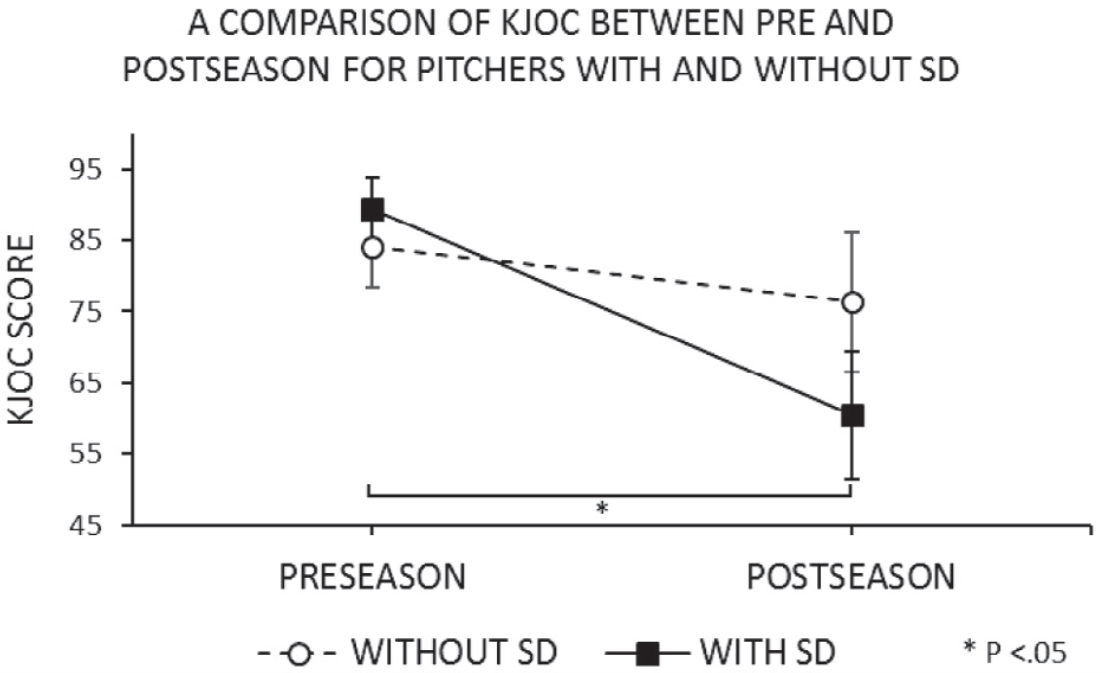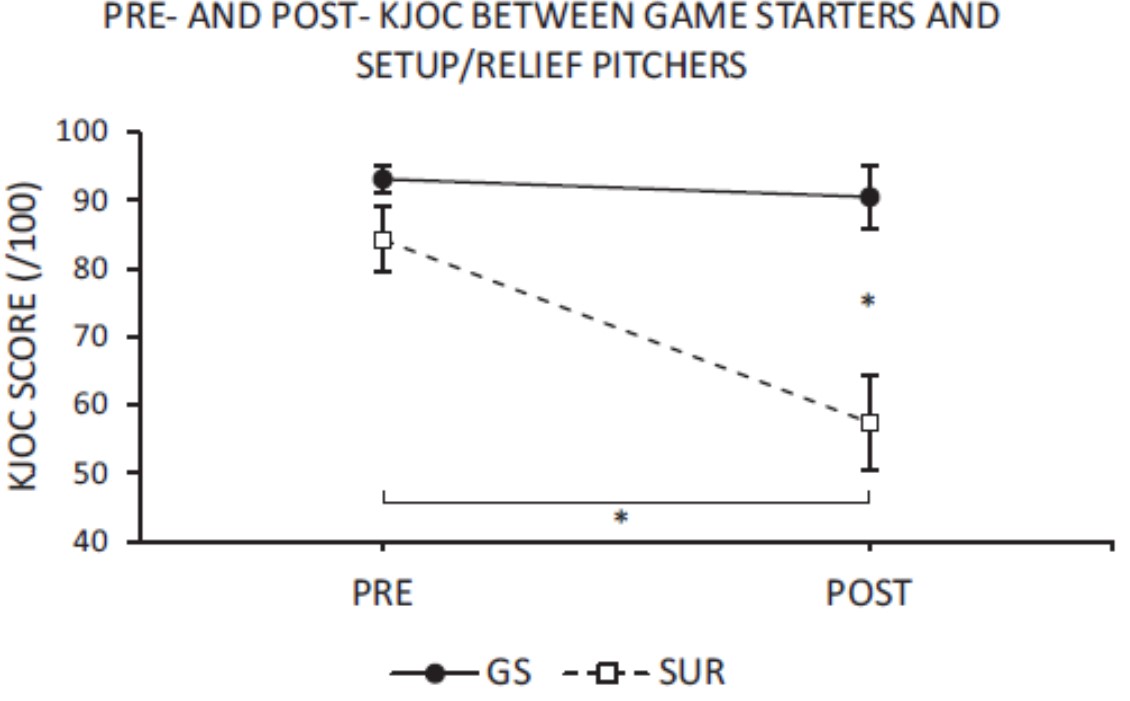腕の上下運動中において僧帽筋上部線維、下部線維、前鋸筋、三角筋前部線維の働きを筋電図で左右比較してみると、利き腕(投球)側の僧帽筋上部線維は非利き腕側に比べ有意に低く、一方で利き腕側の僧帽筋下部線維はそれに比べ有意に高かった。
2013年にKibler氏らで’Scapular Summit’と題詞、肩甲骨運動異常(Scapular Dyskinesis)について権威ある学者間で同意文が作成された(Br J Sports Med, 2013)。論文は興味深く、今までさまざまな視点から投球肩障害メカニズムが議論されてきたが、肩甲骨運動異常がその一つの評価になるのではないかと思った。なにより肩甲骨運動異常が選手の肩の障害リスクに関係しているとのことであった。
肩甲骨運動異常テスト
肩甲骨運動異常テストとは肩甲上腕リズムにおいて肩甲骨の位置が異常であるかを視覚的に評価する方法である。つまり静的状態でなく腕の上下運動の中で肩甲骨の動きを評価することである。しかしこれまでの肩甲骨運動異常テストはさまざまな方法で取り組まれ、たとえば運動負荷はゼロ(0)から両手首に5 kgまで、腕の上下運動も矢状面、前額面、肩甲面と多岐に渡り、さらに上下運動速度も各2秒から5秒と異なった。これらの違いは先行研究の被験者に患者からさまざまな選手が含まれたからであった。
そこで私らは腕の上下運動を屈曲伸展と外転内転とで肩甲骨周辺筋の働きを比較することにした。その際、運動負荷は0、1.8、3.2 kgのリストカフを両手首に付け、運動速度を毎秒のメトロノームに合わせて選手に肘を伸ばしたまま腕の上下運動をしてもらった。運動中左右の僧帽筋上部線維、下部線維、前鋸筋、三角筋前部線維の働きを筋電図を用いて比較した。選手は大学1部に所属する肩に痛みのない現役野球選手28名であった。

屈曲伸展運動の動画→:flex sd test
結果は、運動負荷に関係なく利き腕側の僧帽筋上部線維の働きが非利き腕側に比べ有意に低く、一方で僧帽筋下部線維はそれと比べ有意に高かった。前鋸筋も同様に屈曲伸展において利き腕側が有意な高い値を示した。特に、僧帽筋上部線維と下部線維の働きが種目特異性を示していたことに関心を抱き、今後のリハビリトレーニングの研究に多くのヒントや手がかりを与えた。


左上の図は肩甲骨運動異常テストにおいて屈曲伸展運動中の僧帽筋上部線維の筋電の働き。右上の図は同テスト中の僧帽筋下部線維の筋電図の働き。縦軸が最大筋力時から筋電値の割合、横軸の各1から5(秒)は腕を上げていて、6から10(秒)は腕を下げている時系列である。各折れ線左は負荷0 kg、中央は1.8 kg、右は3.2 kgのリストカフを付けた時である。折れ線の赤は利き腕側で、黒は非利き腕側を示している。利き腕側と非利き腕側の僧帽筋上部、下部線維の働きがそれぞれ有意に違っていることが分かった。
測定の中で高校生の時に関節唇(SLAP)損傷鏡視下手術を受けた投手がいた。この投手は常に肩の痛みを訴えていただが4年生でもあってシーズン最後まで投げ切った。次回は、この選手の筋電図の特徴を説明する。
3.2 ㎏の負荷で最大屈曲位から腕を下げる
腕を最大に上げた屈曲位から下げる運動は、遠心性(伸張性)筋収縮で行われている。求心性(短縮性)収縮に比べ筋電図の働きは有意に低下する。さらに腕を横に上下運動(外転内転)に比べ前方での(屈曲伸展)運動はより肩甲骨の動きの異常を引き出しやすくする。こうしたことから肩甲骨運動異常テストは左右3.2 kgのリストカフを付け最大屈曲位から5秒かけて腕をスムーズに下げることにした(添付動画参照)。
全米大学スポーツ(NCAA)D1に所属する大学野球チームになるとほぼ毎年チーム内のトップ選手はマイナーリーグにドラフトされる。したがって肩甲運動異常テストで用いる運動負荷は選手の体格、運動レベルを考慮に入れる必要があるだろう。